- 書類選考に通過しなくて困っている
- 論理的な文章を作りたい
40代前後になると転職したくても書類選考にすら通過しなくなってきて、多くの人が応募書類の書き方に悩みます。
そこで本記事では履歴書のなかでも志望動機の書き方を説明します。
起承転結で書く人が多いのですが、その書き方、実はNGです!

志望動機がうまく書けない…俺って文才ないかも…
書き出しから締めくくりまでの文章構成を見直して、採用担当者に刺さる志望理由にしませんか?
また、意外に見落としがちなのが口コミのリサーチ。
その企業から内定をもらった人が、応募したときの体験談を投稿していることがあります。
無料登録なので、チェクしておいて損はありません。

\無料登録で300万件以上の口コミ/

- 大手通信企業の元SE
- 業界歴15年のWeb解析士
- 携わったSNSは約100件
- Google Analytics認定資格
履歴書の志望動機の書き方:書き出し~締めくくりまで|起承転結はNG!
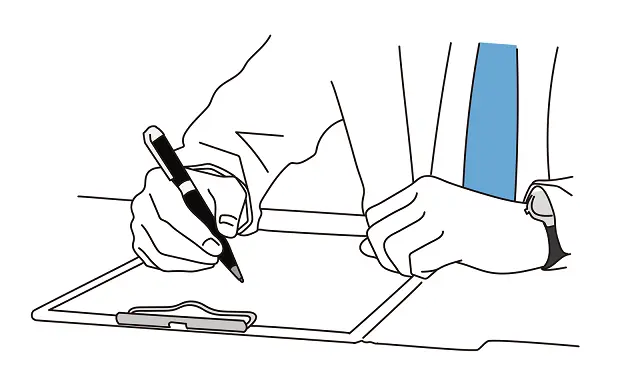
履歴書の作成で最も重要なのは、自分の熱意をアピールすることです。
そのための絶好の材料が『志望動機』ですが、冗長だったり支離滅裂な内容ではマイナス評価になります。
自分の熱意をうまくアピールするためには論理的な文章が必要です。
書き出しから締めくくりを論理的に組み立てるために、起承転結という文章構成はやめましょう。
履歴書の書き方|志望動機は起承転結NGの理由
採用担当者は短時間で多くの履歴書に目を通さなければいけません。
さらには、 採用以外の業務も担当しています。
そうなると、要点の分かりにくい起承転結型の文章は不利に働くおそれがあります。
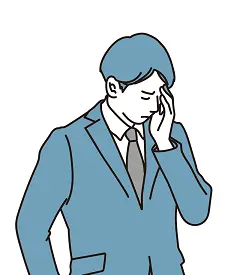
じゃあ、どうすればいいの?
こんなときは、【双括型】が絶対にオススメです。PREP法とも呼ばれています。
以降では、この双括型について詳しく見ていきたいと思います。
なお、志望動機の作成には転職会議が参考になります。
多くの口コミが掲載されているので、「内定が出るのはどんな人?」といった傾向をつかめるかもしれません。
それだけでなく、採用担当者に刺さるネタが眠っているかも!
▼ 300万件以上の口コミは貴重な情報源です。
余談:採用の裏側を少しだけ公開
私は過去、業務の一環として応募書類を見る機会がありました。そこで少しだけ採用の裏側をお話します。
比較的条件の良い待遇で求人を出したところ、幸いにも多くの応募がありました。
しかし、送られてきた応募書類の文章は、『型』を意識していないものが多かったことをよく覚えています。
そうした文章は結論にたどり着くまでに時間がかかって、読むのが大変でした。

要は、何を言いたいのが分かりにくいのです。
内容の把握に時間のかかる応募書類は総じて、評価が低い傾向にありました。
履歴書の志望動機の書き方|書き出し~締めくくりは、双括型が◎
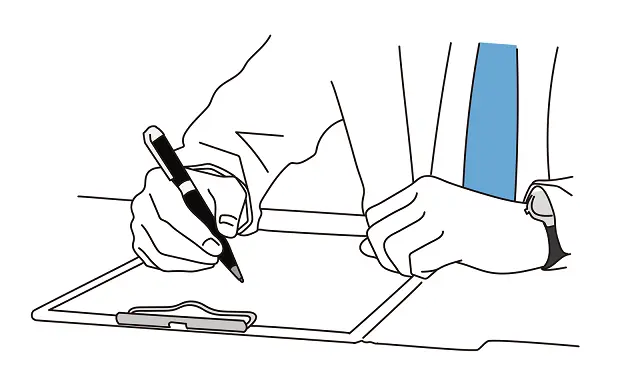
『双括型(別名:PREP法)』とは、次のパートから構成される文章のことです。
結論部分を最初と最後の2回繰り返すことから、【双括型】と呼ばれています。
具体的には次のような構成になります。
- 結 論
- 説 明
- 具体例
- 結 論
まず最初に、結論部分(志望理由を端的に書いたもの)を先頭に配置します。
これが書き出しパートです。
結論を書き出しに持ってくる理由は、自分の主張をすぐに把握してもらうためです。
採用担当者にとって分かりやすい記述になるので印象がよくなります。
また、【双括型】の狙いはこれ以外にもあります。それが下の内容です。
総括型の隠れた狙い
志望動機全体を読んでもらえる!
たとえば、最初に何らかの意見を目にしたら、その理由を知りたくなりませんか?
『この先も読んでみようかな』とウズウズした担当者が、後半部分にも目を通すというわけです。
では以降で、双括型の構成要素である結論(書き出し)/説明/具体例/結論(締めくくり)をそれぞれ説明します。
1.「結論」パート

【結論】は最初に!
志望動機の書き出しでは、「私は~のため、貴社の〇△職を志望しています」など、志望理由を端的に記載します。
友人宛の私的なメールならこの書き方は唐突かもしれません。
しかし履歴書はビジネス文書であり、読んでもらう相手は多忙な採用担当者なので、この書き出しで問題ありません。
その際、転職会議の口コミも参考にしましょう。
応募先企業の雰囲気や求めている人材などの情報が掲載されていることがあります。
それにマッチするような内容を端的に盛り込めば、かなりのアピールになるはずです!
▼ 300万件以上の口コミは貴重な情報源です
最初にこちらの主張を伝えれば、「どうしてそう思うのか?」という興味を抱かせることができます。
そうすれば、年齢や職歴など他の応募者に比べて不利な点があったとしても、志望動機を読み進めてもらえます!
2.「説明」パート

【説明】は論理的に!
このパートが一番の腕の見せどころです。
支離滅裂だったり論理が破綻していればそこでアウト!筋の通った説明にしましょう。
では、『筋の通った』とはどのような状態なのでしょうか。
それは『論理的』ということです。 『論理的』 とは『矛盾のない』結論を導くことです。
つまり、『筋の通った』状態とは『矛盾のない』ことを意味します。
例 題
たとえば、A・B・Cという3つの事象があったとします。
そしてAならばCという命題を「矛盾のない」ように説明してみます。
- A→B
- B→C
- ゆえにA→C
これならば、AならばCということに納得感がありますよね。
これを実際の志望動機にあてはめてみると、
- 前職で~の業務を担当し、〇〇の重要性を痛感した。
- こで〇〇の効率化を図り、業績を~%向上させた。
- この経験を活かし、より高いレベルで〇〇を行いたい。
上記の例はザックリと考えたものなので、厳密には三段論法になっていませんが、論理的な志望動機になっているはずです。
もちろん、無理やり三段階におさめる必要はなく第四段や第五段になってもかまいません。
要は、 『筋の通った』説明によって無理のない結論を導ければOKです。
3.「具体例」パート

【具体例】で説明パートに説得力を!
『具体例』パートの役割は、説明部分に説得力を持たせることです。
いくら矛盾のない説明ができたとしても、それを客観的に証明するものがなければ説得力に欠けますからね。
そこで、具体例によって説明部分を補強して、説得力のある志望動機に仕上げていきます。
「~%向上させた」などの数字を伴う実績を使いましょう
4.「結論」パート

最後にもう一度、【結論】でダメ押し!
そして最後に、最初の『結論』を記載して、志望動機をダメ押しします。これが締めくくりに該当します。
パッと見では、くどいと思うかもしれません。
しかし、最初と最後の計2回繰り返すことで、自分の主張を採用担当者に強く印象付けることが可能になります。
これによって、あなたという存在を採用単相者の記憶に残せることができるのです。
『書類選考に通過しない…』とお悩みの方は、ぜひ一度お試しください!
ちょっと一息
ツールを使用した志望動機の作り方は↓の記事で説明しています。
本記事の内容をあらかじめ頭に入れておくとさらに効果的です。
そして、家庭用プリンタでA3の履歴書を印刷する方法はこちらの記事をどうぞ。
まとめ)履歴書の志望動機の書き方:書き出し~締めくくりまで

以上、『履歴書の志望動機の書き方』と題して、書き出しから締めくくりかたまでを説明しました。
ビジネスの世界では論理的な文章が何より求められます。
そのため、【総括型】の志望動機を作成しましょう。
分かりやすいだけでなく、しっかりしたビジネス文書を作成できる応募者という印象を与えることができますよ。
また、転職会議を併せて利用しましょう。内定者や応募経験者による口コミほど強力な武器はありません。

300万件以上の口コミは貴重な情報源です。
登録無料なので、使って損はなし!
次の3つの記事で内定獲得の糸口が見つかるかもしれません。
転職でお悩みの方はぜひどうぞ。
それではまた、次の記事でお会いしましょう!

質問は気軽にコメントへ!
【関連記事】
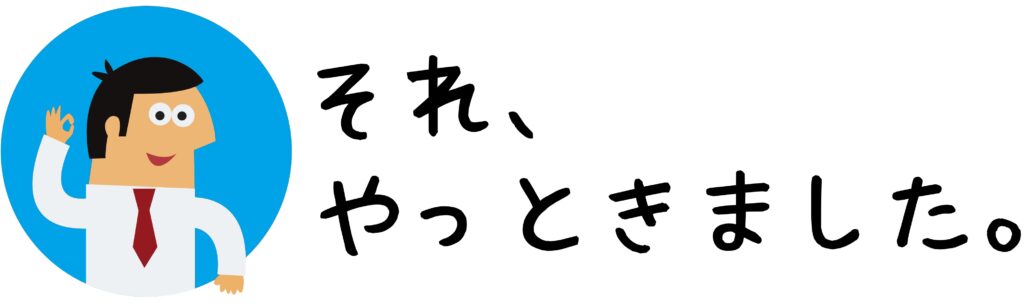
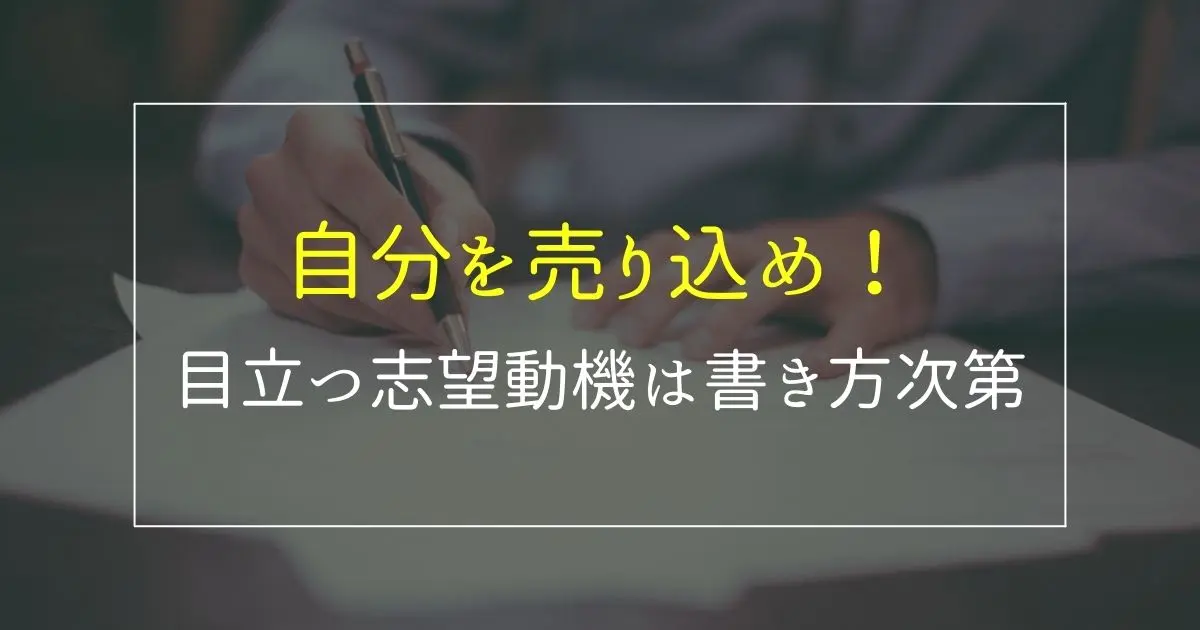
コメントはお気軽にどうぞ!